こんかいはー、「なかなか物を捨てられなかったり部屋のモノを減らすのに苦労している片づけられない人に向けて、ものを減らすための5つの考え方を紹介します。
ちなみにこの記事は、掃除のできない人の考え方9選のシリーズ4つ目「物を捨てることがもったいないことだと思っている」になります。
こんな悩みを持つ方におすすめ
- 後悔するのが怖くて、物を捨てられない
- 自然と物は増えていくけど、減ってはいかない
- 「これはいらない!」と突き放せない
部屋を片付けるときに、毎回「いる」か「いらない」かを考えるのは、ものすごいパワーを使い疲れます。
そのため、なかなか掃除が進まないといった状況に陥りやすくなります。
どうして悩んでしまうのかというと、「もったいない」と心のどこかで思っているからです。
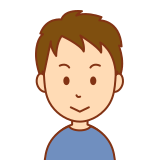
あんまり「もったいない」って思ったことないような気もするけど…
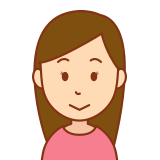
心の中で「もったいない」とそのまま言っていることは少ないかもよ
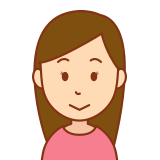
例えば
- これ高かったんだよな
- もしかしたら……
とかね
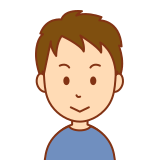
なるほどね!
今回の記事では、もったいない精神をなくして物を減らせるような、考え方や対策を紹介していきます。
片づけられない人は「もったいない」で思考停止する

片づけられない人は、掃除中に「いる」「いらない」で迷ったときに、「もったいない」と感じ、思考停止してしまいます。
そして、「今は、置いておこう」とずっと保留にしてしまうのです。
「この健康器具最近使ってないなー」
「捨てようかな?」
「でも高かったんだよなー」
「どうしようかなー」
「捨てるのも面倒だし、いつかつかうかもしれないし、今捨てなくてもいいか。」
といった感じ。
おそらく片づけられない人も、なぜもったいないのか。なぜ必要なのか。といった理由はぼんやりながら、浮かぶと思います。
もったいないと思うものに理由がないときは、ありません。
必ず何かしらの思い入れがあります。
「いつか使うかもしれない」「友達にもらったから」なども立派な理由です。
しかし、もったいないと思ってしまう理由が分かっていても、このもったいないと思う感情に正面から向き合って、「いる」か「いらない」かを毎回決めるのは大変です。
片づけられない人は、ここでいつも思考停止してしまうのです。
片づけられる人になるためには、そこからさらに考えます。
どの「もったいない」は切り捨てるのか。
などを考えていくのです。
このとき、一つ一つに対して、決断していくことはとても大変で、パワーを使います。そのため、もったいないの基準をはっきりさせる必要があります。
「もったいない」の基準が決まれば掃除が楽になる

たくさんのモノを片付け始める最初に、もったいないの基準となるマニュアル(もったいないの取扱説明書)を作ります。
「いる」「いらない」の決断を楽にするためです。
物が少なくなれば、「いる」「いらない」の決断回数も減って、考えなければいけないことも少なくなるので、必然的にマニュアルがなくてもやっていけるようになります。
しかし、マニュアルなしでやっていける人は、片づけられる人になって、さらに片づけを継続できる人なので、汚部屋の住人からすれば、雲の上の人といっても過言ではありません。
では、もったいないの基準とマニュアルについて考えていきます。
「いる」「いらない」を判断をするためのヒント
どのように「いる」「いらない」を判断していくのかを、「もったいない」を意識して、基準を考えます。
基準を作るときのヒントになるものは5つあります。
- 家の面積に対して、物が占めているお金を計算する
- 家の中に物が何個あるのかをひたすらに数える
- 物は必要ではなくて、思い出のトリガーが欲しいだけ
- 「もったいない」ですべてを捨てないといけないわけではない
- 生活の動線に重要なものではない
家の面積に対して、物が占めているお金を計算する
あまり意識している人はいませんが、人が家に住むときにお金が必要なように、モノを置くためにもお金が必要なのです。
すると、これは毎月1畳に対して1万円を払っていることになります。
そしてあなたのベッドは1畳半を占め、ベッドの下の有効活用もせずに、隣にタンスと棚が0.5畳の幅を取っている。
さらに、勉強机にテレビ台があって、本棚も小さいながらにある。
といった状況をイメージします。
このとき、収納付きのベッドにしてタンスの分の0.25畳を減らせたなら、毎月2500円浮かせられることができると言えます。
あなたが服を脱ぎ散らかしたり、適当に物を床の上に置いたりして、その分の場所を有効活用できていない状態になると、それは無駄にお金を払ってしまっていることと同じです。
もし買ったときの値段が高かったけど、上手く扱えずに損をした。と思いながらもずっと持っていたら、それはさらに損をしていることになります。
時間が経つにつれて、使えもしないモノが空間を圧迫するという、マイナスがさらに増えていくだけになります。
(0.25畳分のタンスを4か月放置していたら、1万円を損するように)
自分の家だから自由なのではなく、自分の家だから無駄遣いをしたくないという気持ちを持つことが大切です。
家の中に何個のモノがあるかをひたすらに数える
これは部屋中の、テレビや棚、歯ブラシに本や、鉛筆に至るまでのすべてのモノをひたすらに数えて、いま家に何個のモノがあるかということを把握するというものです。
棚の中にしまってあるモノも数えます。
タンスの中の服の数も数えます。
(靴下は2つ合わせて1つと数えましたが、そこらへんは個人個人で決めるので十分でしょう。)
ちなみに、自分の部屋にあるモノを数えただけで、約600個のモノがありました。
自分の部屋だけで、です。
そして、あれ?これなんか、無駄に多くない?という気付きも結構ありました。
この方法は、家全体の持ち物を把握することで、自然と家のモノの増えすぎを制限しよう。といった気持ちが生まれてきます。
とてもシンプルながら、なかなか強力な方法です。
物そのものが必要なのではなくて、思い出のトリガーが欲しいだけ
小学校で使ったものを見つけると、「あの頃は○○だったなー」などと懐かしい気持ちになります。
そして、これはやっぱり捨てないほうがいいかなーと思って、「いる」を選んでしまいます。
ですが、ここで大切なのはあの頃の思い出であって、小学校で使ったものそのものではありません。
小学校で使ったもの自体は、思い出のトリガーとして使われているだけなのです。
思い出のトリガーとなれば良いのだから、小学校で使ったもののほとんどは写真に撮って、あとは捨てるべきです。
ただ、すべてを問答無用で写真に撮って捨てるというのは、心境的に少しきついものがあります。
なぜならどうしても実物と写真では臨場感、実物の存在感に大きな差があるからです。
したがって僕は、両手に収まるだけ(目安として10個以内)の実物の思い出のトリガーを残して、あとは写真に撮って捨てています。
実物の思い出のトリガーがあることで、強く思い出を引き出してくれて、写真よりもさらにあの頃を広げてくれます。
すべてのモノを捨てることが必ずしも良いわけではありません。
「もったいない」という感情との妥協点を見つけたほうが、スムーズに行動に移すことができることもあります。
思い出の品は、できるだけ段ボール1箱分に収まるようにします。(宝箱の感覚)
「もったいない」で、すべてを捨てないといけないわけじゃない
「もったいない」と考える人が特に恐れていることがあります。
それは捨てたことによる後悔です。
しかし、実際に捨ててみればわかるのですが、逆に言えば捨ててみないとわからないのですが、捨てたことで後悔することは99%の確率でありません。
少し後悔するとしても、許容できる範囲です。
なぜなら、代わりが効いたり、これは必要なんだなと学んだうえで新しく買えるモノがほとんどだからです。
しかし、代わりが効かないモノを捨てるのは難しいものもあります。
先ほどの思い出の品や、記念の品、絵画など、今は確かに使わないけど大切なものだったり、使うという感じではなく存在するだけで生活や感情を豊かにしてくれるモノです。
こういったものを何でもかんでも捨ててしまうと、代わりが利かないのであとあと後悔しやすいです。
逆に実用性が高いものは、代わりがある場合が多いので、後悔することはほとんどありません。
したがって、使っていないからといって全てを無理に捨てる必要はないのです。
代わりが効かないモノの「いる」「いらない」を考えるときは、心や生活を豊かにしたり、華やかにしてくれているかを考えると良いと思います。
貰い物を忘れたくなければ、写真を取っておけばよいのです。
心や生活を豊かにするためには、生活する空間を自分がデザインするという感覚を持つことが大切です。
生活の動線を考える
生活の動線というのは、普段の生活の中で自分が動く流れです。
例えば、私たちは玄関から家に入りますが、あふれんばかりの靴が玄関に散乱していたら家に入りづらいです。
簡単に言うと、これが生活の動線を邪魔しているということです。
そのベッドが自分の絵やの空間を圧迫し、毎回少しよけたりしながら自分の部屋で生活するのは、少しずつのちりつもですがストレスになります。
こういう場合は、少し無理をしてでもベッドを変えるか、ベッドに合わせて部屋を模様替えするべきです。
この少しの違和感、使いにくさの積み重ねから、面倒くささが現れて、汚部屋に発展したり生活習慣が乱れていってしまうからです。
生活の動線を少しだけ邪魔しているというのは、生活の中で慣れているので気づきにくいことが多く、意識しないと見つけられないことが多いです。
そして、実際に改善してみないと、こんなにストレスになっていたんだなということが実感できないことがほとんどなので、
一度生活の動線というものを意識しながら生活してみることがおすすめです。
終わりに

「もったいない」とうまく付き合えれば、「片づけられない人」は卒業
「片づけられない人」と「片づけられる人」の差の一つに、どこに対してもったいないと思うかというものがあります。
「片づけられない人」は物に対して、もったいないと考えていましたが、「片づけられる人」は、お金や生活に対してもったいないを考えています。
固定観念、当たり前の感覚が違っているのです。
しかし、どこの考え方が固定されていて、ズレているのかに気づいてさえしまえば、その考え方は変えることができます。
「もったいない」の基準を変えることができれば、「片づけられない人」は卒業です。
なぜなら、必要なものと必要じゃないモノの明確な基準を持って家のモノを減らす決断ができるようになるからです。
あとはゆっくり捨て方をグーグルに頼りながら、捨てればよいだけです。
あとは面倒くさいとの戦いですが、もったいないの感覚が分かってくると、「邪魔。なんでこれが家にあるの?」といった感じになってくるので、
モノを減らすのは意外と面倒くさくならないのです。
いらないモノを見つけて捨てたときは、歯磨きをして、歯みがきのミントの爽快感を求めるのに似ています。



コメント